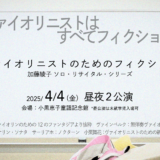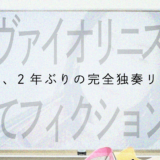評者:西村紗知
写真:©︎YAMADA Satoshi
形式(かたち)を呼吸する ─ 加藤綾子 ヴァイオリン・リサイタル2024
2024年10月9日 19:00開演
代々木上原 ムジカーザ
J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015
灰街令:Palimpsest and Coda for 1001(初演)
西村朗:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番〈炎の文字〉
デュティユー:ヴァイオリンとオーケストラのための協奏曲〈夢想の樹〉
この日のプログラムに並んだ作曲者名を見て、それから『形式(かたち)を呼吸する』というリサイタルのタイトルを一瞥したら、さまざまな意匠、楽式、様式のサンプル集のようなものを会場に居合わせた人々は聞いたのだろう、と何も知らない人ならそう思うかもしれない。
私が聞いたのはそれ以上のことだったはずである。
19世紀のことになるが、かつて音楽学者・批評家のエドゥアルト・ハンスリックは“音楽の内容は響きつつ動く形式である”(ハンスリック著・渡辺護訳『音楽美論』岩波書店、1960年、76頁)と定義した。
形式イコール内容、という境地に至った形式主義的美学を標榜するハンスリックの『音楽美論』は今現在でも読まれる機会がある。この仕事に対する私の印象を述べるならば、彼は音楽を「科学(Wissenschaft)」の俎上に載せるべく、きっちり完結したものとしての「音楽作品」に論及する対象を絞り、伝統的に子弟間で伝達されてきたアフェクテンレーレやフィグーレンレーレの類が含んでいる内実を、ばっさり切り捨てていった、というところだ。私はこの本を読み終えたとき、どうして、ここまで隙のない論理なのに、私の経験がこれを跳ね返してしまうのか、論旨に頭では納得できるのに身体がいまいちついていかないのか、とても不思議な気持ちになった。この理論が完成品の音楽作品から議論を出発させているからだ、と思うに至った。声部ごとにばらしたり楽節ごとに分割したりして音楽の稽古をする人なら、もっと別の理論を構築したのかもしれない。

ヴァイオリニストである加藤綾子は、「形式」をもっと広い意味で「かたち」として捉えている。加えて問題意識を、その「かたち」よりもむしろ「呼吸」の方に、もっと言えば「呼吸」の困難さの方に向けている。プログラム冊子に記された「あいさつにかえて」には次のような文言がある。
なんとなくヴァイオリニストというかたちを目指して、音楽をするために、ずっと息ができなかった。息の仕方を鍛練するより、かたちを叩き、溶かし、流し込み、すこし冷まして、また叩くことのほうが、ずっと大事だった。息の仕方を忘れられたので。
どういうことが言われているだろうか。「かたち」と名指されているものは捉えようによって様々である。例えば、実際の音の連なりによって構築された「かたち」以外にも、「型」と呼ばれるようなもの、ひいては制度や慣習というところまでが「かたち」と名指されているもののうちに含まれているのではないか、と考えることも可能ではある。しかしながら、「かたち」の多義性もさることながら、より重要なのは、上の文言のように「かたち」が「息」なるものと二元的に対立していることの方である。
“ずっと息ができなかった”という事態の深刻度合いは、“息の仕方を鍛練する”という言い回しにすでにあらわれてしまっている。「鍛練」とは第一に金属をきたえるという意味をもつのであるから、むしろ“叩き、溶かし、流し込み、すこし冷まして、また叩く”という、「かたち」に対して行われる行為の方に属するものだろう。つまり、「鍛錬」という「かたち」の側にあるある種のイメージが、「息の仕方」という「かたち」と反対側にあるものの方にも及んでしまっている。「息」には、これを引き起こす「仕方」もろとも、自らの証立てとなるところの言葉すら無い、と言うべきか。
それだから、「あいさつにかえて」では先の引用部分ののちに、“かたちとは風船みたいなものかもしれない”、あるいは“息を忘れたみなさんに、わたしのかわりをお願いする”というような、ある種の相補性や行為の代替性を目指す言い回しが出てくるのかもしれない。風船とは、息を吹き込む者との関係のうちにある、呼吸を通じ相補的に変わっていく「かたち」である。それに、なるほど確かに、演奏会とは集団で行う呼吸のことかもしれない。

さて、最初はJ.S.バッハ『ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015』。華やかできらびやかな音色に、「かたち」は第一段階として、やはり金属的な、「鍛錬」のイメージをもつものかもしれないと思う。第1楽章、A、あるいはEの長音がすうっと伸びて、そのあとフレーズが続いていく。最初に伸ばした一つの音の響きのうちで、音の動きをまとめ上げていくような感覚に、この「かたち」の無駄のなさを想う。第2楽章のアレグロは、ハキハキと捌くようなフレージング。第3楽章、伴奏の左手の動き、跳躍と隙間の多い音型をヴァイオリンが補っていく。終楽章は再び活発に。ピアノの的確なアーティキュレーションとヴァイオリンの奏でる伸びやかなカーブとの対比が楽しい。
「かたち」とは、剥がれ落ちて、形骸化したものが後ろに残されていく、新生化のプロセス自体。灰街令『Palimpsest and Coda for 1001』は、内容的にも質感に関してもバッハと対をなしている。BWV1001に対し、これをパリンプセストに見立てるがごとく、部分的に書き換えを施したりコーダを書き加えたりした作品だ。書き換えは、元の作品が何か聞いてわかる程度に留めてある。出だしのフレーズよりも終止形が書き換えられている印象を強く持った。グリッサンドで上に向かって音の線がずれていく。運動の軌跡が脱臼し、書き変える前の作品がもっていた、別の可能性が実体化していくようである。コーダは長音をスル・ポンティチェロでゆったり伸ばして、時間が停滞したふうであった。電子音響のノイズの感覚が、ヴァイオリンのための書法に落とし込まれたような感じにも聞こえた。
「かたち」とは、「かたち」自身を破棄していくようなもの。西村朗『無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番〈炎の文字〉』の序盤は、A音付近、微妙に音高の異なる音を別々の弦が鳴らし合い、やがて声部が離反したり、また寄り集まったりして展開する。重音のひずみは即興的に聞こえるが、異なる音型やリズムのパターンが順を追って登場するので、譜面に書き込まれている情報の多さを感じる。だが譜面に書かれたものは、着実に演奏者の身体に火をともしていって、もはや書かれたもの以上となった。しっかりと屈みこんで重心を低くして演奏するため、身体パフォーマンスの側面もある。その身体は、即興と作品の真っ向勝負の場でもあったかもしれない。

最後はデュティユー『ヴァイオリンとオーケストラのための協奏曲〈夢想の樹〉』。「かたち」とは、これを扱うものの力によって、まさに目の前でかたちづくるものへと成っていくところのもの。楽章間がアタッカでつながっていて、音楽の「かたち」そのものが大樹の比喩となるような作品だと思った。それと率直な感想を言うならば、地道な稽古の成果がうかがえる演奏だった。ピアノによるオーケストラ譜のリダクションとは、音を選んで元の「かたち」を削減していくことではあるが、同時に「かたち」を復元することでもある。できる限り元の譜面から音を拾っていかねばならず、ヴァイオリニストの意見も重要だ。弦楽器群のざわめきや、鐘の音色の打楽器群がつくる音響の奥行、これらをピアノ一台で代替せねばならない。けれども、光の拡散や、陰影の移ろい、たくさんの小さな「かたち」が合わさって、たったひとつ、その音楽だけがここでは大樹となることができていた。
「息」は「かたち」の間を通っていく。ひとつの音楽はたくさんの「かたち」によって成り立っている。それぞれ「かたち」の間には隙間がある。生み出されていった「かたち」の数々が、「息」の居場所を自分自身とともにつくっていく。
今や、ハンスリックのテーゼは留保を付けられるか、あるいは書き換えられるべきかもしれない。例えば、「その「かたち」を響かせ動かしていくのは「息」であろう」と。